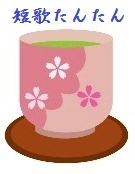2012年04月05日
今月のみそひともじ-H24年4月
八重山毎日新聞を発表の場として、「八重山短歌会」があります。私は高校一年の頃から投稿していたのですが、会の皆さまにじかにお会いして短歌会に出席するようになったのは、成人してからです。その後ヤマトゥに渡り、「くぐひ」という同人誌に20数年間所属しておりました。たまたま短歌雑誌の広告で見て入会した結社だったのですが、釋迢空(折口信夫)の息のかかったお弟子さんたちが、迢空の教えを継いで続けている短歌会でした。折口信夫が民俗学者として沖縄にも関係が深かった事もあり、沖縄の会員も何人か所属しておりました。その中には、後に琉球新報の「琉球歌壇」の選者となる嶋袋全幸先生もいらっしゃいました。
ヤマトゥに出て来て私は、諸々の想像もしなかったような身辺異変を経験することになるのですが、「くぐひ」での貴重な知己は、私の中で大きな拠りどころとなり今の私があるとも言えます。ほんとに感謝しております。多くの先生方はあの世に逝ってしまわれましたが、今でも年賀状のやりとりをしている方が数名いらっしゃいます。
故人となるの繰り返しで、主宰が何人か替わりましたが、全く知らない方に引き継がれて間もなく、私は会をおいとま致しました。そして今、数年前から古巣の「八重山短歌会」に戻って来て現在に至っております。旧知の会員は、新絹枝さまを含め数人しかいらっしゃいません。
昨年暮れまでの一年間、八重山毎日新聞紙上で毎週「八重山の花調べ」を短歌とともに執筆していらっしゃる大竹蓉子先生(第4回短歌研究新人賞受賞者)を選者として迎えての歌壇でしたが、先生のご事情により退任されました。大竹先生とは、東京八重山文化研究会でお目にかかっておりました。今年の1月からはまた選者不在の、短歌作品掲載のみの短歌会になっております。
毎月3首の発表ですが、新聞掲載後にこのブログに「今月のみそひともじ」として掲載させて頂きます。新聞掲載が毎月末あたりですので、翌月の初め頃の掲載になると思います。
今月の3首は、石垣帰省の時に詠んだものです。
ふるさとの変はりしものと変はらぬものこもごも味はふ帰郷初日や
八つの子の観察の目や再会の挨拶の間にほくろ数当てる
三つの子の著き好奇心珍客の挙手投足を都度訊きて来る

登場人物の二人。左が八つ、右が三つ
ヤマトゥに出て来て私は、諸々の想像もしなかったような身辺異変を経験することになるのですが、「くぐひ」での貴重な知己は、私の中で大きな拠りどころとなり今の私があるとも言えます。ほんとに感謝しております。多くの先生方はあの世に逝ってしまわれましたが、今でも年賀状のやりとりをしている方が数名いらっしゃいます。
故人となるの繰り返しで、主宰が何人か替わりましたが、全く知らない方に引き継がれて間もなく、私は会をおいとま致しました。そして今、数年前から古巣の「八重山短歌会」に戻って来て現在に至っております。旧知の会員は、新絹枝さまを含め数人しかいらっしゃいません。
昨年暮れまでの一年間、八重山毎日新聞紙上で毎週「八重山の花調べ」を短歌とともに執筆していらっしゃる大竹蓉子先生(第4回短歌研究新人賞受賞者)を選者として迎えての歌壇でしたが、先生のご事情により退任されました。大竹先生とは、東京八重山文化研究会でお目にかかっておりました。今年の1月からはまた選者不在の、短歌作品掲載のみの短歌会になっております。
毎月3首の発表ですが、新聞掲載後にこのブログに「今月のみそひともじ」として掲載させて頂きます。新聞掲載が毎月末あたりですので、翌月の初め頃の掲載になると思います。
今月の3首は、石垣帰省の時に詠んだものです。
ふるさとの変はりしものと変はらぬものこもごも味はふ帰郷初日や
八つの子の観察の目や再会の挨拶の間にほくろ数当てる
三つの子の著き好奇心珍客の挙手投足を都度訊きて来る
登場人物の二人。左が八つ、右が三つ
Posted by あんあん at 05:05│Comments(0)
│短歌、俳句